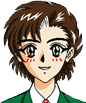 |
ハーイ、皆さんこんにちはー!
楓ちゃんでーす。
今日は「どうよく」についてでーす。
それでは講師のいぶきさん、どぉぞー! |
 |
か、楓ちゃん、ヤケにハイテンションね、
何か有ったの? |
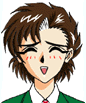 |
え?い、いやー、ホラ、久しぶりだからサ。
なんかこぅ、アッピールしたいなー、
なんて、ハハ・・。 |
 |
はぁーい!
私知ってまーす!何でおねーちゃんが
ハイテンションなのかぁ・・。 |
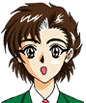 |
あ!!コラ!こずえ!
シー!シー!言っちゃ駄目! |
 |
ま、まぁ、ソレは置いといて、
そろそろ始めましょうか・・。 |
 |
今日のテーマは「動翼」です。
「動翼」と言うのは、読んで字のごとく
「動く翼」の事です。
これには「エルロン」「ラダー」
「エレベーター」があるの。
後、今回はついでに「フラップ」についても
説明します。 |
 |
「動く翼」?それじゃー何?
鳥みたいに翼がバサバサ羽ばたくっていう訳? |
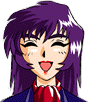 |
あはは、、違うわよ。
動翼は飛行機をコントロールをするのに
欠かせない物なのよ。
つまり、操縦するときに動く「可動式の翼」な訳。 |
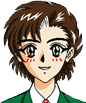 |
あ、そっか。
じゃぁ操縦桿に繋がってる翼な訳ね。 |
 |
そうそう。 |
 |
うーん、
飛行機ってどうやって方向変えたり上昇したり
してるか、今まで考えた事もなかったけどぉ・・・。 |
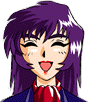 |
そうね、
でもそんなに難しい原理じゃないのよ。
それじゃぁ、まず動翼の基本的な
理屈から行くわね。 |
 |
第一回の「翼」の時にやったと思うけど、
二人とも「揚力」って覚えてる? |
|
|
 |
あ、はい。どうして飛行機が飛んでるか、
っていうアレですよね。
翼の上と下では圧力差があって、
下の圧力の方が強くて
上に上がって行くんですよね? |
 |
そう。じゃぁ、翼をどうすると揚力が
増大するかは覚えているかしら? |
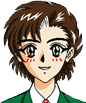 |
「迎え角」が大きくなると
揚力も大きくなるのよね。
それで、大きすぎると失速するの。 |
 |
はい、その通りね。
飛行機をコントロールする「動翼」も、
この原理を使っているのよ。 |
|

 |
 |
この図を見て。
上の状態が動翼をニュートラルにした場合。
下の状態が動かした場合。
さて、揚力はどうなるかしら? |
 |
んん~。見た感じ、下の方が揚力大きそう、
でも空気抵抗も大きそうですね。 |
 |
おお!?梢ちゃんズバリ大正解!
そう、揚力と同時に「抗力(ドラッグ)」も
大きくなるの。良く気づいたわねー。
偉い偉い。 |
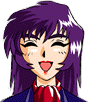 |
翼の上下の中心線をキャンバー線って
言うんだけど、
①の状態は仮想キャンバーが深くなる、
つまり同じ方向から風を受けていても
より大きな揚力を得ることになるの。
つまり、右の図で行くと、より上に上がろうと
するのね。②はその逆で、キャンバー線
が浅くなるから揚力が減る訳。 |
 |
それじゃー、実際にどうやって飛行機が
動翼によって動いているかを、それぞれ
説明するわね。 |
|

 |
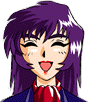 |
まずはエレベーターから行くわね。
その名の通り、飛行機の上下動に関わる
動翼なの。これは水平尾翼についてるの。
場所は右の図の通りね。 |
|
 |
 |
さて、ここで問題です。
右の写真は飛行機の操縦に使う
操縦輪(コントロールホイール)なんだけど、
引いた場合は飛行機は上昇して、
押した場合は降下します。
では、その時に水平尾翼の動きは
それぞれどうなると思う? |
 |
う、うーん。①が揚力が大きくなるから
上昇で、②が揚力が小さくなるから降下です。 |
 |
うーん、残念。その逆なの。 |
 |
えぇ!?何でですかぁ!? |
|

 |
 |
確かに、梢ちゃんの言うとおり、①は揚力が
大きくなって②は小さくなるけど、
ここで考えて欲しいのは、通常、飛行機の
水平尾翼は機体の最後尾に付いていると
言う事ね。①の状態で後ろの揚力が
大きくなった機体は機首を下げて降下します。
逆に②の状態で後ろの揚力が小さくなった
機体は機首を上げて上昇するの。
|
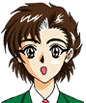 |
へぇー!!成る程ぉ! |
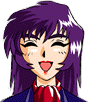 |
じゃぁ次は横の動きよ。ラダーについての
質問は楓ちゃんに答えて貰おうかな♪ |
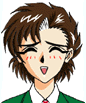 |
え?あたし? |
|

 |
 |
大丈夫!今やったエレベーターを横にして
考えればスグに判るわよ。ラダーは垂直尾翼に
付いています。さて、ラダーはラダーペダルで
操作します。つまり足で操作する訳ね。
ラダーを右に蹴れば飛行機は右旋回。
左に蹴ったら左旋回しますが、
①②のどちらが右旋回時でしょうか?
|
 |
え、えーっと・・・。
①の場合は右の方の圧力が大きくなるから、
尾翼は左に押されるでしょ?・・・だから機首は
反対方向の右に・・・。 |
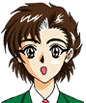 |
あ!判った!①が右旋回で②が左旋回ね! |
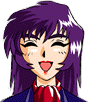 |
はーい、ご名答! |
|

ラダー
 |
 |
じゃぁ次はエルロンね。
これはラダーやエレベーターと違って、ちょっと
変わった動きをするの。
エルロンの取り付け位置は左右主翼の後縁に
有るんだけど、右と左が上下反対方向に
動きます。つまり、片方の揚力を増大させて
もう片方の揚力を減少させる訳。 |
 |
そうする事で、ラダーとは違って機体は
進行方向を軸に回転する格好になります。
エルロンは操縦輪を右に切ると右旋転、
左に切ると左旋転するんだけど、
操縦士は調和の取れた旋回をするには
ラダーとエルロン、時にはエレベーターを
全て使わないといけないの。
これを「3舵の調和」と言っています。 |
 |
うーん、自動車なんかと違って、ただ
ハンドルを右左に切るだけじゃー
駄目なんですね。 |
|

 |
 |
そうね、計器に「すべり計」(通称「ボール」)
と言うのが有るんだけど、
旋回中に上手く調和が取れていないと、
このボールが、左右どちらかにズレるの。
操縦士はこれが計器の中央になるように
旋回します。これを俗に「ボール・センター」
と呼んでるわね。 |
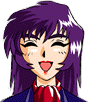 |
ちなみに、エレベーターでの動きを
「ピッチング」(ピッチ)、
ラダーでの動きを「ヨーイング」(ヨー)、
エルロンでの動きを「ローリング」(ロール)
と言います。 |
 |
さて、最後にフラップね。
これは、今までの3舵とはちょっと使い方が
違うの。主に離着陸の時に使用します。
フラップは日本語では「高揚力装置」
と言われてるわね。 |
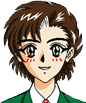 |
高揚力装置? |
|
 |
 |
そう、飛行機は、なるべく少ない速度、
短い滑走距離で離着陸したいんだけど、
そこで考えだされたのがフラップです。
巡航時には①図の様に主翼に格納されていて
使用時に操縦席の「フラップレバー」で
操作します(図②)
通常何段階かのフラップ角度に
調整できるようになってるわね。
|
 |
フラップを出すことによって、キャンバー線が
変わって、揚力と抗力が増大します。
結果、失速速度が少なくなって、巡航時
よりも少ない速度で離着陸出来るの。
つまり、滑走距離も格段に短くて済む訳。 |
 |
へー、良く考えられているんですね。 |
|

 |
 |
初期の「単純フラップ」から、
大揚力を発生する「三重隙間フラップ」迄、
数多くのフラップが考案されてきました。
又、大型機には翼の前面に「前縁フラップ」
を装備した物も有ります。 |
 |
第二次大戦位迄は、フラップは空中戦を
有利に戦うためにも頻繁に使われていました。
これは旋回性能が良くなるからなの。
中でも日本海軍の戦闘機「紫電改」には、
「自動空戦フラップ」という物が付いていました。
これは水銀柱で作られた「Gメーター」が、
ある設定されたGを感知すると(旋回中は
バンク角が深くなればなる程強いGが掛かる)
自動的にフラップが出て、旋回半径を小さく
するという優れ物でした。 |
 |
はい、今日の講座はこれでおしまい。
・・・所で楓ちゃん、さっきの話だけど、
一体何が有ったのかな~♪ |
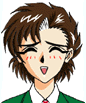 |
え!?いや・・、たはは、な、なんでも
ないわよ~、や~ね、いぶきさん。 |
 |
えへへ!
は~い!!私、知ってま~す!!! |
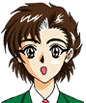 |
あー!?コ、コラァ!もぉ!!! |
|
 |





























